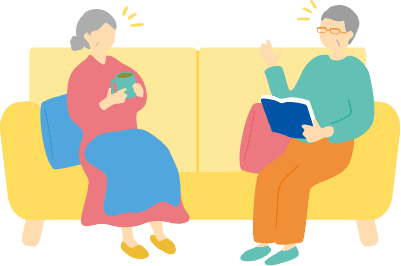この思いは私だけに限らず、歴史教室・京都に参加された方の共通認識ではないかと思います。
まず、1日目の河内将芳氏による「醍醐寺三宝院門跡と豊臣秀吉」をテーマとした座学は、2日目の散策に向けての見学視点の明確化や期待感の醸成にとても効果的でした。
特に、正しくは「さんぼういん」と濁音読みすることや、秀吉との関係で重要人物となる座主・義演(准后)の日記を史料として「醍醐寺の花見と三宝院」について詳細に解説してくださったことは有り難かったです。
そして、2日目の僧侶の方による法話と3つのエリア(伽藍エリア、三宝院、霊宝館・仏像棟)の散策は、私にとって初めての見学ということもあって、まさに感動の連続でした。中でも、仏師・快慶の初期の傑作である弥勒菩薩坐像を間近で拝観した時は、思わず心を打たれました。
また、散策中に気づいたこととして、どの見学場所でも僧侶の方に誰かしら熱心に質問する姿が見られて、この歴史教室に寄せる興味・関心の高さが印象に残りました。
最後に、今回も私たち参加者に懇切丁寧にサポート・対応してくださった公立学校共済組合友の会スタッフの皆様、誠に有り難うございました。