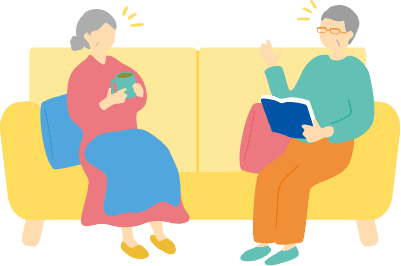退職後はいろいろな分野の勉強をしたかったので東京の某大学の講座を受講した。仏像、陶磁器、古事記、万葉集、歌舞伎並びに、実演鑑賞、文楽、労働法、きくち体操(実技)等である。続けるうちに、ただ聞いてノートをとるだけでは物足りなかった。天秤の一方に乗っている腑甲斐なさ、不十分さだった。課題を出され、次週発表する講座に軸を変えた。例えば英米短篇の翻訳の授業だった。講師より割当てられ、次週会員の前で和訳し、会員の質問に答える形の授業だった。五、六十人の中で赤恥にさらされるのは精神的につらかったので、自分で周到に辞書を引き、参考文献をも熟読した。自らアクティブに授業に参加する体勢が性に合った。万葉集では、漢字だらけの万葉仮名では理解不能だったので聞くことに集中した。つまり受講するには天秤の均合いを取ることだった。しかし、やはりアクティブに授業に参加する方が私には記憶に残っている。当地よりローカル線、新幹線に乗り換え下車してまた地下鉄に乗車、キャンパスまで歩くのは身体にも良かった。コロナ禍でオンライン講座になり挫折した。ともあれ、人生に於いて何かに挑戦し、足跡を残せるのは楽しいと感ずる。また退職後の生きた証にもなるだろう。
「自分に合った受講をする」 栃木県 T.H. (88歳)
18
この記事が気に入ったらぜひいいね!をお願いします。