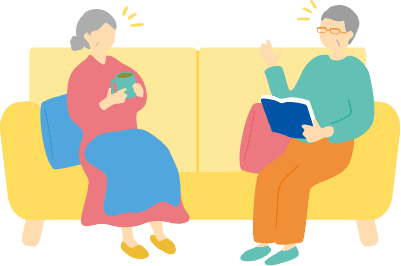四天王寺を訪れたことがなくても「四天王寺式伽藍配置」という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。南から北に向かって中門、五重塔、金堂、講堂が一直線にならび、ぐるりと回廊で囲む伽藍配置です。これは飛鳥時代の古い建築様式で、四天王寺が日本最古の寺院といわれる証しのひとつです。いくたび罹災しても伽藍形式を変えずに再建され続け、聖徳太子が建立した1400年前のたたずまいを今に伝えています。
座学では『日本書紀』にも記される四天王寺の由緒について学び、散策では「極楽浄土の東門」として信仰を集めた四天王寺式の伽藍や重要文化財の石の鳥居などを巡り、通常非公開の絵堂では聖徳太子の生涯を描いた障壁画の絵解きをお楽しみいただきます。